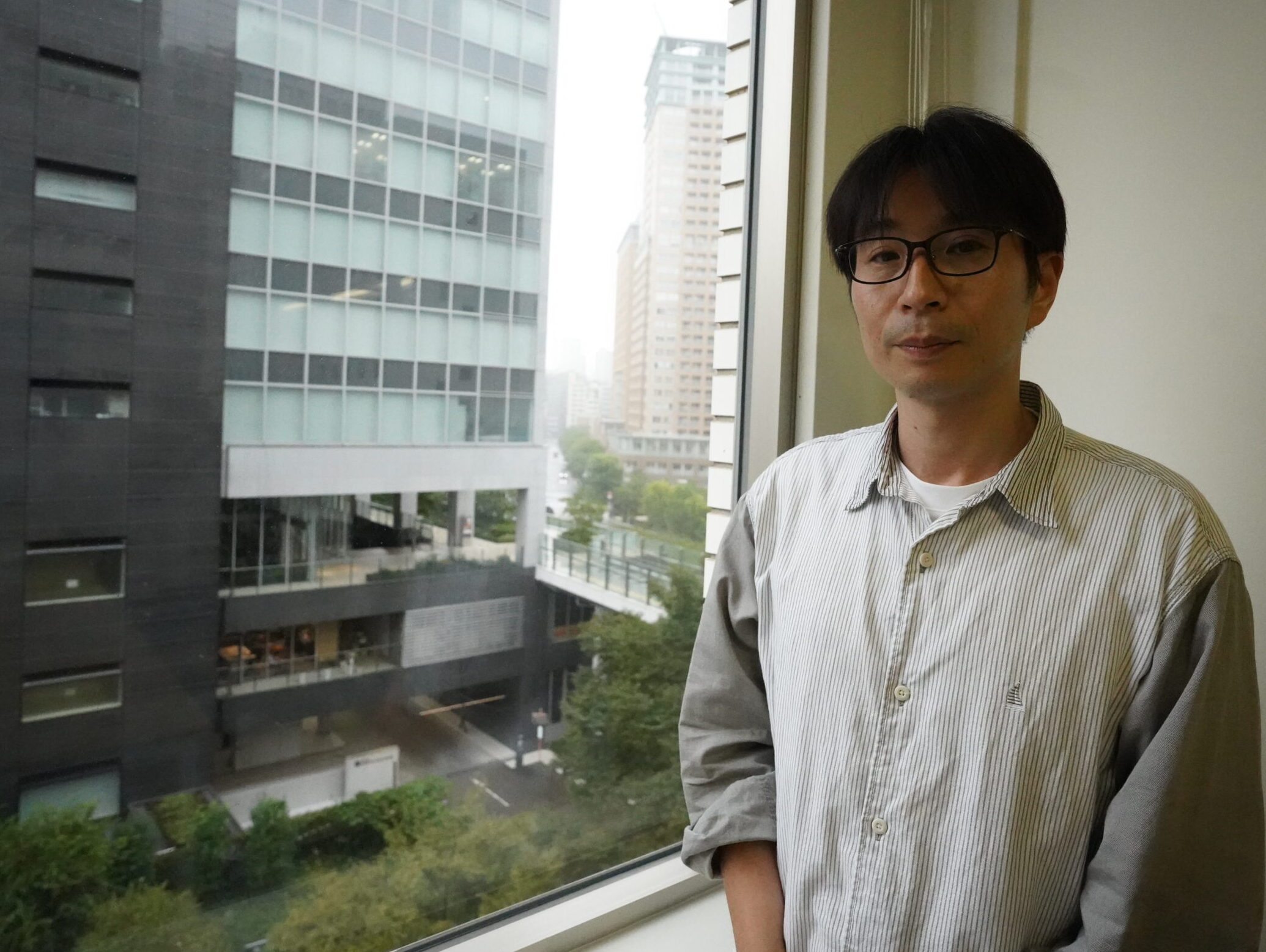私は大学で建築を専門に学んだ後、ゼネコンに就職しました。私は転職で翔栄エンジニアリングに入社しています。元々はマンションの設計を行っていましたが、今では主にプラント系配管(液体・気体・粉体)の設計や工場用ユーティリティ配管の設計にまで幅を拡げています。
翔栄エンジニアリングという会社は不思議な会社で、本当に色々な分野に取り組んでいます。そのため、メンバーの専門性も多岐にわたります。例えば、下水道処理場の配管設計をやる人もいれば、発電所の配管設計をする人もいる。私みたいにいわゆる「箱物」と言われるマンションから今ではユーティリティ設備をやっている人もいます。
当社が三興バルブHDグループに参画することで、今ではさらに色んな分野にチャレンジできるのがとても楽しいですね。
拡がったのは分野だけじゃない。当社は東京に本拠地を置いているので、必然的に関東が中心となる。でも、三興バルブHDグループや特に一緒に仕事を進める機会が多い、エフライズは全国にまたがります。エリアも大きく拡がりました。
さらに、設計という仕事柄どうしても「要件を満たす」ことに一生懸命になりやすい。しかし、設計というのは全体のプロセスで言うと一部でしかない。色んな人が関わります。例えば設計するからには、お客様が何か実現したい目的がある。これは主に営業を担当する人がお客様と一緒に決めるわけです。さらに見積を作るためには、設計に加えて、「拾い出し」というどのような部材が必要かを考える必要がある。そして、部材がきちんと順番に正しく届くのか?そして、それらを使って構築していく職人さんたちがどのように組立、据え付けをするのか?さらには据え付けした後にどのように動かすのか?そこまで考えて設計をします。
ただ、それは設備の機能の話。さらには他の設備との関係性、耐震性などを満たすことができるのか?等々考えることは本当に沢山あります。
また、設計という業務は個人の仕事という印象が深いかもしれません。でも、何人もの人が協力しながら設計をするんですよね。それができあがった瞬間は本当に嬉しいです。
実は、社内には文系出身の人も設計に関わっています。もちろん、理系の人に比べたら最初はよく分からないこともあるかもしれませんが、踏ん張ることができれば上手く行くことが多いです。だいたいの仕事は何とかなるもんで、仕事は必ず終わると思っています。そのような楽観的な感覚もこの仕事に必要なのかもしれませんね。